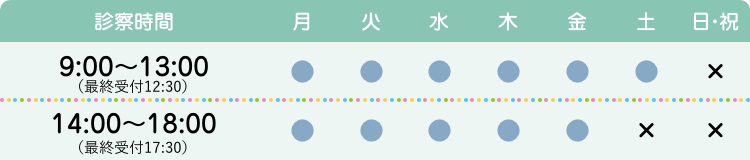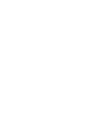福岡市南区の内科、呼吸器内科「よこやま内科」
アレルギー性鼻炎は、ダニ、花粉、カビ、動物の毛やフケなどに反応して、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどの症状が起こります。通常アレルギー症状を抑えるために、抗ヒスタミン薬の内服やステロイド薬の点鼻などを行います。一部に自然と症状が軽くなる場合がありますが、アレルギーですので、基本的には長期間付き合っていく必要のある病気です。
このようなアレルギー性鼻炎ですが、根本的に治す可能性のある治療として舌下免疫療法という治療法があります。
これはアレルゲン物質の成分を少量含む舌下錠を、毎日舌下内服することで、鼻炎症状を出にくくする治療法です。
治療期間は3年から5年と大変長いのですが、およそ8割の方で鼻炎症状が軽くなったり、完全になくなるような改善効果が期待できます(残念ながら2割の方には効果がないということになります)。
また、舌下免疫療法を行うと、その後他のアレルゲンによるアレルギー症状の出現や気管支喘息の発症が抑えられると報告されています。
治療の対象となるのは、現在のところスギ花粉、もしくはダニを原因とするアレルギー性鼻炎の方のみですので、事前に血液検査でスギ花粉、ダニに対するアレルギー反応の有無を確認する必要があります。
なお、スギ花粉が原因の場合、花粉症症状の出現する期間(2月から5月)には治療を開始できませんので、6月以降に治療を開始することになります。
アレルゲン物質を直接内服するため、副作用の出現が心配されますが、これまでの報告ではアナフィラキシーという重症のアレルギーを起こすことは非常にまれで、のどのかゆみや唇のはれのような軽い副作用は起こりますが、抗ヒスタミン薬の内服で改善し、多くの場合、治療経過とともに出にくくなります。初回は原則として院内で内服していただきますのでご安心ください。
最低3年間と根気強く行う必要がある治療ですが、鼻炎症状から解放される可能性のある唯一の治療法ですので、長引く鼻炎症状でお困りの方にはぜひ一度ご相談いただければと思います。
舌下免疫療法について詳しい情報をご希望の方は、こちらもご参照ください。
気管支喘息では、慢性的に気管支で炎症が生じており、その結果として、気管支が狭くなったり、刺激に対して反応しやすい状態となり、咳、喘鳴、呼吸困難などの症状が引き起こされています。
ステロイド吸入を行い、気管支に直接薬を届けることで、気管支の炎症を抑えて、喘息症状をコントロールすることができます。
ほとんどの方はステロイドと気管支拡張薬の吸入を併用することで、喘息症状がコントロールできるのですが、一部に吸入治療を行なっても十分に症状が改善しない場合があります。
そのような場合、次の治療選択肢として、ステロイド内服、および生物学的製剤の使用が挙がります。
ステロイド内服は有効な治療ですが、長期間内服すると、免疫力の低下、糖尿病、骨粗鬆症などの副作用が出現することがあり、できれば避けたい治療です。
生物学的製剤とは、病気の発症や悪化に関わっている物質を直接ブロックするように設計された薬剤です。喘息に限らず、リウマチ、潰瘍性大腸炎、乾癬などの慢性的な炎症性疾患で使用されています。
気管支の炎症を火事に例えると、ステロイド吸入は放水して消火するような治療ですが、生物学的製剤は火元となる火薬に着火するのを直接防ぎ、そもそも火事が起きないようにする治療です。
生物学的製剤は注射剤ですので、薬剤によって異なりますが、月に1回から2回投与する必要があります。
吸入薬による治療でも喘息症状が十分に効果が得られていない方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
10月1日で開院1周年を迎えることができました。
開院後しばらくは1日に来院されるのは10名程度で、正直に申し上げると不安を抱えながらの船出でありました。
しかし、1年間が経過し、咳や喘息でお悩みの方、高血圧や脂質異常症のような生活習慣病の方、発熱・かぜ症状の方、健康診断やワクチン接種などでのご来院を含め、5,000名を超える方にお越しいただき、従業員一同大変感謝しております。
2年目も引き続き地域の内科医、および呼吸器専門医として、ご来院いただく方の健康管理にお役立てできればと考えております。ちょっとした症状、お悩みであっても、気軽にご相談いただければと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
まだまだ暑いですが、9月以降徐々に気温が低下していきます。
朝晩の気温差があるとかぜやアレルギー性鼻炎症状が出やすくありますが、秋の花粉症の可能性もあります。
秋の花粉症は8月から10月に症状が出ることが多く、原因植物としてブタクサ、ヨモギ、カナムグラが挙げられます。
これらはいわゆる雑草ですので、春のスギ花粉とは異なり、比較的近い範囲にしか花粉は飛散しません。
この時期になると鼻炎症状の出る方で、近所にこれらの雑草がある場合、近寄らない、可能であれば除草するとよいかもしれません。
※ 除草する場合はマスクやメガネを装着して、花粉を浴びないようにお気をつけください。
<ブタクサ>

<ヨモギ>

<カナムグラ>

胃食道逆流症(逆流性食道炎)は長引く咳の主な原因のひとつです。
胃食道逆流症は胃酸が食道に逆流することによって生じる症状のことで、典型的には胸やけや呑酸(酸っぱいものの逆流)のような食道症状を伴いますが、食道症状を伴わない例も多くあります。
なぜ胃酸の逆流が咳を起こすのかといいますと、逆流した胃酸により食道下部に存在する迷走神経が刺激されたり、咽喉頭まで逆流した胃酸の直接的な刺激により咳が生じます。
食道裂孔ヘルニアのような逆流しやすい状態の方は、就寝時に横になった状態で逆流しやすいのですが、そうでない場合は胸やけなどの症状がほとんどなく、主に日中に会話や食後しばらくしてからなどの場面に咳が出やすくなります。
また、食道症状を伴わない場合、咳払い、声がれ、咽喉頭の違和感のような症状を伴う咳があれば、胃食道逆流症の存在を疑います。
長引く咳の原因として胃食道逆流症を疑った場合、検査で確認することは一般的ではなく、まずは治療薬に対する反応を確認します。
治療としては胃酸分泌を抑える薬を内服します。
胸やけなどの症状は比較的速やかに改善するのですが、咳や声がれのような症状の改善には数ヶ月を要することがあります。
したがって、長引く咳の原因として胃食道逆流症の関与を疑う場合は、根気強く内服治療を行う必要があります。
薬以外の治療として、胃食道逆流を起こしやすくする原因を除くことも有用です。
肥満、飲酒、カフェイン、チョコレート、炭酸飲料などは胃食道逆流を起こしやすいことが知られており、該当する場合、減量や飲食習慣の改善を行うことが望ましいです。
また、就寝前の飲食を控えることや腹部を締め付けるような衣服を避けることも必要です。
咳喘息や感染後咳嗽などが咳の原因である場合でも、咳き込むことで腹圧が上昇し、胃酸の逆流を引き起こし、さらに咳を引き起こすような悪循環を招くことがありますので、吸入治療に加えて胃酸分泌抑制薬を併せて使用することもあります。
長引く咳の原因として、胃食道逆流症は比較的頻度の高い原因と考えられますので、咳が長引いてお困りの方場合、一度は治療を試してみる必要があると考えられます。
※ この記事は「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019」を参考に記載しました。
長引く咳の原因の一つとして肺がんがあります。咳の原因としての頻度は非常に少ないのですが、生命に関わる重要な病気です。
一般的に肺がんは無症状のまま徐々に進行しますので、健診などで偶然発見されることが多い病気です。発見する機会のないまま進行が続くと、ようやく症状が出てきます。
肺がんが進行し、気管や比較的太い気管支の表面にまで浸潤した場合に、咳として表に症状が現れます。
肺がんは早期発見し、手術(もしくは放射線治療)を行うことができれば治癒が期待できる病気です。ただし、咳として症状が出てきた場合には、比較的進行していることが多いため、喫煙者など肺がん発症のリスクが高い方は定期的に胸部X線写真の撮影を受けるのが望ましいと考えます。
頻度は少ないものの、長引く咳の原因のひとつとして副鼻腔気管支症候群という病気があります。
慢性副鼻腔炎と気管支炎・細気管支炎・気管支拡張などが同時に存在する状態で、好中球という白血球が副鼻腔や気管支で過剰に炎症を引き起こした状態です。
症状としては咳に加えて、膿性の鼻汁、痰、後鼻漏などがあります。
治療としては炎症を抑える効果のあるマクロライド系抗菌薬の少量長期内服を行います。1-2ヶ月ほど内服を継続することで、鼻汁、痰などの気道分泌が減少し、その結果咳も減ってきます。
マクロライド系抗菌薬にはいくつか種類がありますが、まずはエリスロマイシンを開始することが多いです。治療効果不十分の場合は、クラリスロマイシンへ変更します。
ただし、クラリスロマイシンは肺非結核性抗酸菌症に対する重要な治療薬ですので、事前に痰の検査を行って非結核性抗酸菌の感染の有無を確認しておくのが望ましいです。
マクロライド系抗菌薬の副作用としては下痢、味覚異常などがあります。また、他の薬との飲み合わせが悪い場合があります。
治療経過次第ですが、症状が安定していれば、2年を目処にマクロライド系抗菌薬の内服を終了しますが、症状が再燃した場合は内服を再開し、さらに長期間の内服を行わざるをえないこともあります。
副鼻腔気管支症候群を発症される方は決して多くはありませんが、時々いらっしゃいますので、慢性咳嗽、膿性鼻汁・痰、後鼻漏などの症状が持続する方は、一度は胸部X線写真を撮影し、異常のないことを確認しておくことをお勧めいたします。
※ この記事は「咳嗽・喀痰のガイドライン2019」を参考に記載しました。
高血圧を治療中の方で、なかなか血圧が下がりきらない場合があります。
特に起床時の血圧が高いような場合には、睡眠時無呼吸症候群が潜んでいる可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群とは文字通り、睡眠中無意識に無呼吸、低呼吸(通常より小さな呼吸、もしくは酸素飽和度の低下)を反復的に繰り返す疾患です。
典型的な症状としては、日中の眠気や疲労感がありますが、その他に睡眠中の呼吸困難(窒息感)、朝の頭痛、不眠を自覚することもあります。
その一方で自覚症状のない、あるいは気づいていない方も相当数存在すると考えられます。
高血圧の方の実に30%に睡眠時無呼吸症候群が合併していると報告されています。
睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP治療を受けることで、収縮期血圧 2.6 mmHg、拡張期血圧 2 mmHg とわずかですが血圧が低下します。
特にコントロール不良な高血圧の方の場合は、収縮期血圧 6.7 mmHg、拡張期血圧 5.9 mmHg の降圧効果があるとされます。
血圧のコントロールが不十分な方は、自覚症状がなくても、一度は睡眠時無呼吸症候群が存在する可能性を疑う必要があると考えます。
※ この記事は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」を参考に、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を念頭に記載しています。
新型コロナウイルス感染症の後遺症として咳が続くことがよくあります。咳が続く期間は数週間から数ヶ月にまで及びます。
咳が続く原因として以下のような理由が考えられます。
① 新型コロナウイルス感染に伴い生じた肺炎像が残存しているため
② 気道に感染した新型コロナウイルスが炎症を生じさせるため
③ 新型コロナウイルスが咳を引き起こす神経に感染するため
残念ながら、新型コロナウイルス感染後の咳に対する治療法として、確立したものはありません。
咳に対する一般的な治療薬が主体となりますが、以前からかぜをひいた後に咳が残りやすい方であれば、咳喘息の可能性を考慮して吸入ステロイド薬を使用する意義はあると考えられます。
また、吸入抗コリン薬はウイルス感染による咳感受性(咳の出やすい状態)を和らげることが知られており、新型コロナウイルス感染後の咳にも効果がある可能性があります。
咳を引き起こす神経への影響を抑えられると咳を減らせる可能性が高く、近日難治性の咳に対して発売される予定の薬が効果があるかもしれません(新型コロナウイルス感染後の咳に対して処方できるとは限らないのですが)。
長引く咳は体力を消耗させ、気も滅入らせてしまいます。コロナ禍にあっては周囲の視線も気になるものです。しかし、新型コロナウイルス感染後の咳には必ず終わりが来ますので、症状の強い間は薬を使用して凌げるようにサポートさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症が猛烈に流行しています。
現在流行しているオミクロン株は、比較的軽症で済み、重症化する可能性も低いと考えられていますが、それでも持病をお持ちの方にとっては、心配が非常に大きい状況ではないかと推察します。
気管支喘息の方にとっての新型コロナウイルス感染症に関して、現在以下のようなことがわかっています。
① 気管支喘息の方がそうでない方に比べて、新型コロナウイルス感染症に感染しやすいということはなく、むしろ、気管支喘息の方では、新型コロナウイルスが体内に侵入する際の入り口となるACE2というもの発現量が少ないため、新型コロナウイルス感染症にかかりにくいという報告があります。
② 気管支喘息の方が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、重症化しやすいということはありません。
③ 気管支喘息の方が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合も、吸入ステロイド治療の使用により重症化することはなく、安全に使用できます。
④ 現在の気管支喘息のコントロール状況が悪い人ほど、入院するリスクが高くなります。
以上のことから言えることは、気管支喘息の方が新型コロナウイルス感染症に罹患しても、重症化しやすいということはありませんが、日常の吸入治療を怠り、喘息のコントロールが悪い状態にあると入院のリスクが高まり、また、新型コロナウイルス感染症に対する吸入ステロイド薬の悪影響も乏しいため、基本的な感染対策(3密の回避、マスク、手指消毒)を行いながら、毎日の吸入治療を継続していくことが最も重要である、ということではないでしょうか。